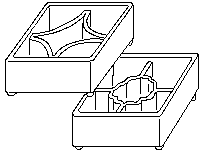- TOP
- 学ぶ・楽しむ
- おうちで学ぶ・楽しむ
- 博物館ディクショナリー
- 陶磁
- 『磁器』(石もの) 染付名花十友図三重蓋物 (『じき』(いしもの) そめつけめいかじゅうゆうずさんじゅうふたもの)
『磁器』(石もの) 染付名花十友図三重蓋物 (『じき』(いしもの) そめつけめいかじゅうゆうずさんじゅうふたもの)
工芸室 河原
1994年12月10日
今回は、生活にもっとも関係のふかい「やきもの」、陶磁器について勉強しましょう。
私たちが日常使っている「やきもの」には、陶器と磁器があります。京都の陶磁器関係のひとたちは、陶器は粘土を材料にしていますから、これを「土もの」と呼び、磁器は磁石をくだいて作った磁土を使うので「石もの」と呼んでいます。材料がちがうため出来上がったものも、見た目からもちがいます。陶器は茶褐色で分厚いものが多く、あまり堅く焼きしまらないので、軽くたたいてみると、少しにぶい音がします。それに対して磁器は、純白にちかく、薄手に作られ、堅く焼きしまっているので、たたくとすんだ高い音がします。
自分が毎日使っているご飯茶碗や湯飲みなどが、陶器なのか、磁器なのか、いちど調べてみて下さい。
さて、この三段重ねの蓋物(ふたもの)
は、磁器で作られています。普通、陶磁器の形は「ろくろ」と呼ぶ回転する円盤のうに陶土や磁土をのせ、回転力をうまく利用して形を作っていきます。しかしこの作品では「ろくろ」を使わず、磁土を板状にして、ちょうど木の板で箱を作るように形を作っています。それをかげ干しし、乾いたところで「素焼き」といって、窯にいれ、700度から800度ぐらいの温度で軽く焼き上げます。そして呉須(ごす)と呼ぶ酸化コバルトの顔料(鉱物質の絵具)で文様を描き、そのうえに窯のなかでとけてガラス質の幕になる「上釉(うわぐすり)」をかけ、1200度から1300度ぐらいの高温で焼きます。そうすると磁土も白く堅く焼きしまり、上釉を透かして、下に描かれた青い文様が見えてきます。しかも全体の10パーセントから15パーセントぐらいは焼きちぢみしますし、その時にそったり、ゆがんだりすることも多いのです。この蓋物も少しゆがみ、重なり具合があっていないところもありますが、技術的な限界で仕方がないことのようです。
この作品は、白地に青で文様が描かれているため「染付(そめつけ)」といわれ、白い布に藍色(あいいろ)の文様を染め付けたものににているところから、こう呼ばれるようになったといわれています。文様は十種類の草花が描かれ、その間に、浄友(じょうゆう)、名友(めいゆう)、佳友(かゆう)、艶友(えんゆう)、清友(せいゆう)、禅友(ぜんゆう)、僊友(せんゆう)、韻友(いんゆう)、雅友(がゆう)、殊友(しゅゆう)の十種類の文字が散らされています。これは中国の宋(そう)時代に十種類の草花がえらばれ、友達になぞらえられたもので、よく絵画のテーマとしても描かれています。
その組み合わせは、ハス=浄友、カイドウ=名友、キク=佳友、シャクヤク=艶友、ウメ=清友、クチナシ=禅友、カツラ=僊友、ドビ=韻友、マツリ=雅友、チンチョウゲ=殊友といったものです。むずかしいかも知れませんが、例えば泥のなかから花をつける蓮や梅の花は、ともに清い心の友達、芍薬(しゃくやく)は魅力ある美しい心の友達などといった感覚は少し理解できるかも知れませんね。
さて、この蓋物は、江戸(えど)時代の終わりごろ、京都で活躍した青木木米(あおきもくべい)(1767~1833)の作品です。木米は若いころから中国の文化にあこがれ、中国陶磁器の書物にであってから、一生懸命勉強し、とうとう有名な陶工になった人物です。
幼いころの名を青木八十八(あおきやそはち)といい、大きくなってからも、この名前にちなんで青木の木と八十八(米)をあわせて、木米を名乗りました。木米は画家としても有名ですが、当時の知識人たちがもとめた、中国風の煎茶(せんちゃ)の道具などを「型」を使って量産し、さまざまな工夫をこらした優れた作品を作り出しました。この蓋物にも上から二段目と三段目に工夫があり、内側にそれぞれ形のちがった五つの区切りを作っています。
料理が交ざりあわないための工夫です。木米は使いやすい陶磁器の製作に工夫をこらした陶工として活躍し、江戸時代末期の京都の「やきもの」界をリードしていきました。この蓋物は、中国的なデザインと日本的な形をみごとに調和させたものということができると思います。